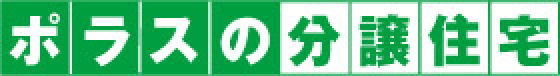肥料
自然に生育している樹木に肥料を与えていません。庭木にはなぜ肥料を与えなければならないのでしょう?
庭木にはなぜ肥料が必要なのか??
自然の状態では、木の根元に落ち葉がたまります。この落ち葉は昆虫や微生物の働きで分解され、肥料になって土に還元され、樹木の養分になるのです。ところが、庭木は掃除をするために養分の供給が不足がちです。ただ庭木は草花のように頻繁に与える必要はなく、生育期に1回、遅効性の肥料を散布し軽く土と混ぜ合わせます。また肥料を与える時期は原則活発に活動する生育期となります。
花をより大きく、美しく、野菜・結実をより美味しく育てる為に多くの養分が必要となり、生育に不足する養分を人工的に補います。

肥料の3要素

有機質肥料
自然の材料を腐植発酵させてつくったものです。
効果が緩やかで遅効性肥料(固形)とも言われています。
堆肥・腐葉土:葉や茎、小枝などを腐植させたもの
バーク堆肥:樹皮、枝などを腐植させたもの
油粕:大豆や菜種の絞り粕
鶏糞:骨粉・魚粉
与えた時からゆっくりと効きはじめ、
長期間効果が持続します。
無機質肥料
化学的に合成されたもので即効性肥料(液体)が主体です。
窒素系、リン酸系、カリ系、配合肥料
・液体肥料
(・肥料固形)
与えたらすぐに効果がありますが、
その時だけ作用しますので定期的に与えます。
庭木が生長しはじめたら・・・
一年以上経過し、すっかり根付いた庭木は土に含まれた水分で十分育ちます。
水を遣り過ぎて常に根が水に浸かっていると、根は呼吸が出来ないために腐ってしまいます。
水の遣り過ぎには特に注意が必要です。
除草
雑草取りも大切な仕事です。
もし、雑草を怠ると背の低い潅木は日光が当たらなくなって生長できなくなりますし、大きい木でも雑草に水分や養分を取られて生育が阻害されます。
その上、なによりも庭の美観が大変悪くなってしまいます。気が付いたとき、まだ背丈が小さいときにこまめに抜き取るようにします。
どのような除草剤があるの?
面積が広いときは除草剤を散布するときがあります。しかし、いかに毒性が低いといっても、有用な植物環境や生態系のバランスを崩す等悪影響を及ぼす恐れもありますので、慎重に散布するようにしましょう。
土壌処理剤:発芽前に薬剤を散布して根から吸収させて枯らす。
移行処理剤(ホルモン系):発芽前に薬剤を散布して根から吸収させて枯らす。
接触処理剤(非ホルモン系):表面に宣布して薬剤のかかった部分を枯らす。
選択性除剤:イネ科以外の植物を枯らす。
非選択性除剤:全ての植物を枯らす。
《除草剤を選択するポイント》
①どんな場所に散布するのか?
②枯らしたい雑草の草丈は?
③枯らしたい雑草の種類は?
④効果が現れるまでに速度は?
⑤除草効果の持続時間は?
⑥散布場所は水が使えるか?
⑦散布面積は?
⑧専用器具(噴射器)はあるか?
病害虫
毛虫が大切な植木の葉を食べてしまった・・・。
急に葉が枯れてきた、元気が無くなった・・・。
どのような除草剤があるの?
樹木も人間と同じでいろいろな病気が出てきます。
その病気の原因は昆虫、バクテルア、ウイルスなどがあります。
そして、人間の場合と同じで、病気になる前にまず予防枝を透かして(剪定)通風と採光をはかることだけでも効果的です。
どのような薬剤を散布すればいいの?
病害虫の原因である昆虫、バクテリア、ウイルスによって散布する農薬も違ってきます。間違った使い方をすると十分な効果が得られなかったり、逆に薬害が生じてしまうこともあります。そこで、まず病害か虫害かを見分け、さらにその種類を調べます。
薬剤の購入と使用に際しては、必ず説明をよく読んで、記載内容にしたがって下さい。
薬剤の選び方のポイント
①虫?病気?を判断しましょう。
・どういう症状がでるか。
・虫の姿が見えないか?
・被害の拡大、蔓延状況はどうか?
②薬剤の剤型、特性、効果等を理解しましょう。
・剤型ごとの利点、注意点を理解する。
・使用場所、規模等の条件に合った剤型を選択する。
③用途、使用方法、使用面積に応じて選択する。
・対象植物名を再確認する。
・植物と適用病害虫が合った薬剤を選択する。
殺虫剤:
デブテックス乳剤、カルホス乳剤、
スミチオン乳剤等
殺菌剤:
ダイセン、石灰硫黄合剤等
病虫害にはどのような種類があるの?
主な病害

ウドンコ病
植物体上にちょうどうどん粉をふりかけたような白色粉状物質を生じる糸状菌病です。対処法としては剪定を行い通風、採光を良くしたり、病葉を焼却したり、あるいはうどん粉病専用防除剤を散布するのが効果的です。

スス病
この病気は葉が黒色スス状物で覆われる糸状菌病です。
通気性や日当たりが不良で多湿環境を好んで発生します。
本病気は吸汁性害虫の寄生が最大の誘因となるので、アブラムシ、カイガラムシを駆徐することが最も重要となります。また、剪定を行い、通風、採光を良くする事も効果的です。
主な虫害

アブラムシ
アブラムシが寄生すると枝の伸長や葉の展開に影響を及ぼします。
また二次的にすす病を併発し、黒く汚染されます。
防除するには剪定によいって通風、採光を良くすると共に、薬剤散布が効果的です。

チャドクガ(茶毒蛾)
葉を食害すると共に、有毒な毛をもっているので、これに触れると激しいかゆみが長く続いてしまいます。チャドクガは薬剤に弱く、市販のスプレー剤でも充分効果があります。