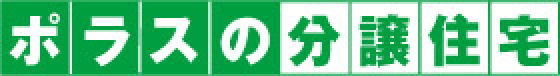耐震性について

阪神淡路大震災と東日本大震災の教訓により、建物の耐震性に大きな注目が集まっています。建物ばかりでなく、土地の地盤についても調査が必要とされています。耐震性とはどのようなことなのか、もう一度考えてみましょう。
建築基準法による耐震基準
1950年に人命・財産の保護・保全を目的とし耐震基準を定めた建築基準法が施行されました。これにより、市街地だけに適用されていた耐震基準が全ての建物に適用されるようになりました。
その後1978年に発生した宮城県沖地震を受け、1981年に建築基準法が改正され、耐震設計法は大きな転機を迎えます。これまでの、震度5程度の中規模地震に対して倒壊しない基準から、震度6~7の大規模地震でも倒壊しないという基準になりました。
また、「保有水平耐力」という概念が持ち込まれました。
建物は地震で大きく揺らされると一部的に損傷を受けますが、これにより揺れのエネルギーを吸収し、建物の被害を減少することができる性質があるため、これを設計に持ち込むことにしたのです。たとえば、柱の一部が壊れることにより揺れが吸収され建物そのものの倒壊を免れたといった事例があります。
その後1978年に発生した宮城県沖地震を受け、1981年に建築基準法が改正され、耐震設計法は大きな転機を迎えます。これまでの、震度5程度の中規模地震に対して倒壊しない基準から、震度6~7の大規模地震でも倒壊しないという基準になりました。
また、「保有水平耐力」という概念が持ち込まれました。
建物は地震で大きく揺らされると一部的に損傷を受けますが、これにより揺れのエネルギーを吸収し、建物の被害を減少することができる性質があるため、これを設計に持ち込むことにしたのです。たとえば、柱の一部が壊れることにより揺れが吸収され建物そのものの倒壊を免れたといった事例があります。
住宅性能表示の耐震等級とは
耐震等級とは、耐震強度により等級1~3に定義されています。等級1では、建築基準法で定められた、数百年に一度発生する大規模地震でも、倒壊、崩壊しない耐震性能であり、これが以降の耐震等級の基準になります。その1.25倍の耐震強度を持つ住宅を等級2、等級1の1.5倍の耐震強度を持つ住宅を等級3と定義しています。
構造計算による耐震設計とは
たとえば、車の衝突実験では、車に人形を乗せて壁に衝突させて実験をする事ができます。しかし、建てた一戸建て住宅をそのまま耐震性能実験をすることはできませんので、建築設計では耐震設計について構造計算により行うことになっています。
建築基準法が構造計算の基準を厳格に定めていますので、これに基づいて構造計算を行います。構造計算に間違いや不正があると、見かけは立派な建物であっても、実際に地震にあった時などに大きな被害を出すかもしれません。このため建築基準法では罰則を定めるなどして建築基準を徹底しています。
建築基準法が構造計算の基準を厳格に定めていますので、これに基づいて構造計算を行います。構造計算に間違いや不正があると、見かけは立派な建物であっても、実際に地震にあった時などに大きな被害を出すかもしれません。このため建築基準法では罰則を定めるなどして建築基準を徹底しています。
木造2階建ては構造計算書が無くても大丈夫か?
■4号建築物の基準
・木造住宅
・階数が2階建て以下
・延べ面積 500平方メートル以下
・高さ13メートル以下
・軒の高さ9メートル以下
そのため、構造計算を簡略化した場合の建物は基準ギリギリに建てられている可能性があり、構造計算をされた建物よりも強度が乏しいのが現状です。
当社の一戸建ては上記に該当する「4号建築物」でもすべて構造計算を行い建てられています。地震の多い日本の住宅だからこそ安心して住んでいただけるよう耐震性に自信を持ってご提案いたします。
・木造住宅
・階数が2階建て以下
・延べ面積 500平方メートル以下
・高さ13メートル以下
・軒の高さ9メートル以下
そのため、構造計算を簡略化した場合の建物は基準ギリギリに建てられている可能性があり、構造計算をされた建物よりも強度が乏しいのが現状です。
当社の一戸建ては上記に該当する「4号建築物」でもすべて構造計算を行い建てられています。地震の多い日本の住宅だからこそ安心して住んでいただけるよう耐震性に自信を持ってご提案いたします。